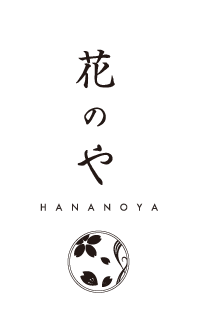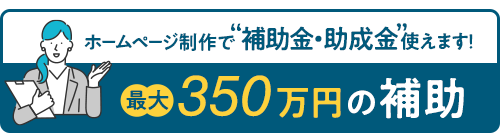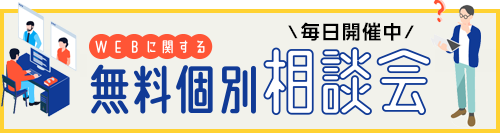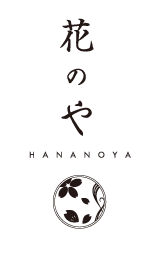一緒に悩み、考える。
つくるだけでなく、
そのあとの物語も、ともに。
どんな会社もサービスも、それぞれにストーリーがあります。
花のやはそれをサポートしながら、お客様の成長を隣で見ていたいのです。
一緒に悩み、考える。
つくるだけでなく、
そのあとの物語も、ともに。
どんな会社もサービスも、
それぞれにストーリーがあります。
花のやはそれをサポートしながら、
お客様の成長を隣で見ていたいのです。
ブログBLOG
- 名古屋のホームページ制作会社 花のや
- 花のやブログ
- Web制作者が意識すべきバリアフリー
Web制作者が意識すべきバリアフリー
アクセシビリティは“配慮”ではなく“成果”の条件
こんにちは、花岡です。最近、猫のトイレトレーニングに失敗して、結構落ち込んでいますが、今回はWeb制作におけるアクセシビリティの話です。Webサイトは「使えること」が成果に直結する時代です。
特にシニア層のネット利用が急増した現在、年齢や障害を問わず使いやすい設計=バリアフリー対応は、成果を上げるための前提条件になりつつあります。
目次
スマホ普及で“全世代ユーザー時代”に
2021年時点で、60代以上のスマホ保有率は80%を超えています。
70代の多くもLINEやブラウザ検索を日常的に使うようになり、これまでWebと縁遠かった層がメインユーザーとして登場しています。
つまり、Webサイトは若者だけのものではないということ。
制作側もその変化に合わせて、“誰にでも使えるWeb”を本気で考える時代になりました。
混同しがちな3つのキーワード
バリアフリー設計でよく出てくる3つの言葉、それぞれに違いがあります。
ウェブアクセシビリティ
障害の有無や年齢に関係なく、すべての人が情報にアクセスできるように設計する考え方。
例:スクリーンリーダー対応、キーボード操作でも使えるUIなど。
ユニバーサルデザイン
最初から「誰でも使える」ことを前提に設計されたデザイン思想。
例:高コントラストの配色、直感的なナビゲーション。
ユーザビリティ
直訳すると「使いやすさ」。
クリックしやすい、迷わず情報にたどりつけるなど、心理的ストレスの少なさも含めた体験全体を指します。
まずは「年齢」を意識するだけでも変わる
すべての配慮を完璧に盛り込むのは難しくても、「高齢ユーザーも使えるか?」という視点だけで、設計の優先度は変わります。
- フォントサイズは16px以上を目安に
- 行間(line-height)は1.6〜1.8程度確保
- ボタンやリンクの間隔を広めに取り、誤操作を防ぐ
将来の自分も対象になるからこそ、年齢配慮は“誰にとっても価値がある”のです。
デザイン性とバリアフリー、どちらが正解?
バリアフリーを優先すると、デザインの自由度が狭まる場面も正直あります。
同系色のデザインや凝ったアニメーションなどは制限されがちです。
それでも私たちは「見る人の使いやすさ」を優先すべきだと考えています。
Webサイトは“作品”ではなく、“使われる道具”だからです。
SEOにも影響する「アクセシビリティ対応」
最近では、Googleの評価基準にもアクセシビリティが含まれています。
Core Web VitalsやLighthouseといったツールでは、操作性や視認性の高さがスコアに反映されます。
アクセシビリティ対応は、SEO対策にもなる時代です。
またAppleやMicrosoftといった大手も、UIや製品設計でこの視点を重視するようになっています。
花のやが意識していること
花のやでは、「誰でも迷わず操作できるWeb」を目指し、
見た目の美しさと機能性のバランスをとった設計を行っています。
特に医療・介護・シニア向けサービスの制作では、見た目よりも体験を優先した構成を採用し、
必要な配慮を最初から盛り込むようにしています。
おまけ:最近のお気に入り
まじめなこと書きすぎたので最後に、最近食べたお気に入りのラーメンを載せておきます。Web制作と同じで、見た目だけでなく“中身”が大事ですね。

人気記事ランキング
カテゴリ
書いた人別一覧
お問い合わせ
Webサイト制作・その他お仕事のご依頼、
ご相談についてお気軽にお問い合わせください。
052-211-9898